『春と修羅 序』宮沢賢治について 、概要・あらすじ・引用文をなぞり、作品解釈や探求を深めながら、自作のイラストで世界観を紹介しています。 物語の要約も含まれているため、作品をすべて読む時間がない方にもおすすめの記事です。
概要:詩集『春と修羅』とは
著者:宮沢賢治 ジャンル:詩集 出版年:1924年(大正13年)、宮沢賢治が自費出版
宮沢賢治の代表的詩集『春と修羅』は、彼の精神的な旅の記録であり、「自然」「宇宙」「人間の心」という三つの層を交差させた作品です。東北の農村での生活体験を詩に昇華させたこの詩集には、四季折々の風景、雄大な自然の力、農作業、動物たち、民俗芸能などが登場します。それらを単なる情景描写にとどめず、賢治は常に「人間とは何か」「苦しみの意味とは何か」を問い続けます。
📚青空文庫にて全文公開中
心に残った引用文×着想イラスト
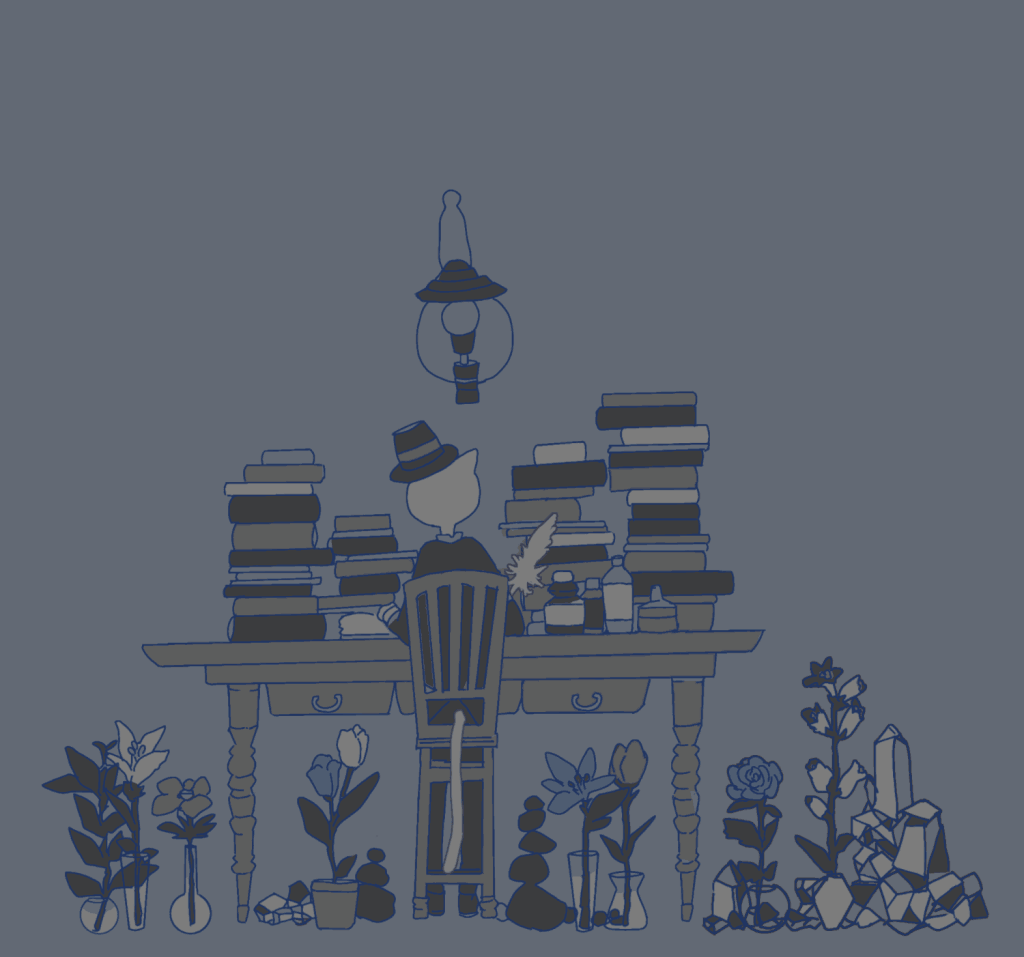
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)これらは二十二箇月の
過去とかんずる方角から
紙と鉱質インクをつらね
(すべてわたくしと明滅し
みんなが同時に感ずるもの)
ここまでたもちつゞけられた
かげとひかりのひとくさりづつ
そのとほりの心象スケツチです
感想×用語解説×考察
この詩の冒頭に出てくる比喩「有機交流電燈」「青い照明」は、一読しただけでは意味をつかみきれません。しかし、そこにこそ賢治の思想の深さがあります。一つひとつ調べながら、直感的に「こうではないか」と思ったことを書き連ねています。内容に誤りが含まれている可能性もありますが、どうかあたたかく見守っていただければ幸いです。
『春』と『修羅』とは?
・「春」は自然の美しさ
・「修羅」は煩悩や苦しみ
有機交流電燈とは?
「有機」=炭素を含む生きた物質。生命体、細胞など。
「交流電燈」=電流の向きと大きさが周期的に変わる電気(交流)による明かり。
→ 明滅する光=生まれては消える命のリズム?
※ 賢治が生きた時代(大正期)は、電気照明がようやく一般に普及し始めた頃。その中で「交流電燈」は最先端の技術であり、彼は当時の科学知識を詩的表現に積極的に取り入れていた。自然と科学、信仰と現実を分けなかった彼の視点は現代にも通じる統合的な思想です。
因果交流電燈 ― 仏教的な光のメタファー
因果交流電燈の / ひとつの青い照明です
「因果」は仏教用語で、「原因」と「結果」のつながりを意味します。「業(カルマ)」と深く関わっており、自分の行いが未来にどう返ってくるかを考える視点?
なぜ「青い」照明なのか?
青という色は、心理的に「冷静」「孤独」「精神性」を象徴。美しさと寂しさが同居した色でもあり、夜の静けさ、宇宙の果て、魂の奥行きを連想させます。
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
→ 光(精神・命)は残り、肉体(電燈)は失われる
死んでも、誰かの心に「ひかり」として生き続ける?
第四次延長=時間+魂の空間
「第四次延長」という概念は、縦・横・高さ(3次元)に「時間」を加えた4次元世界のこと。
科学と宗教、可視と不可視、その境界を自由に行き来する思想?
読後の変化×学び×まとめ
今回は詩集の序文のみを取り上げましたが、他の詩についても、いずれご紹介できればと思っています。

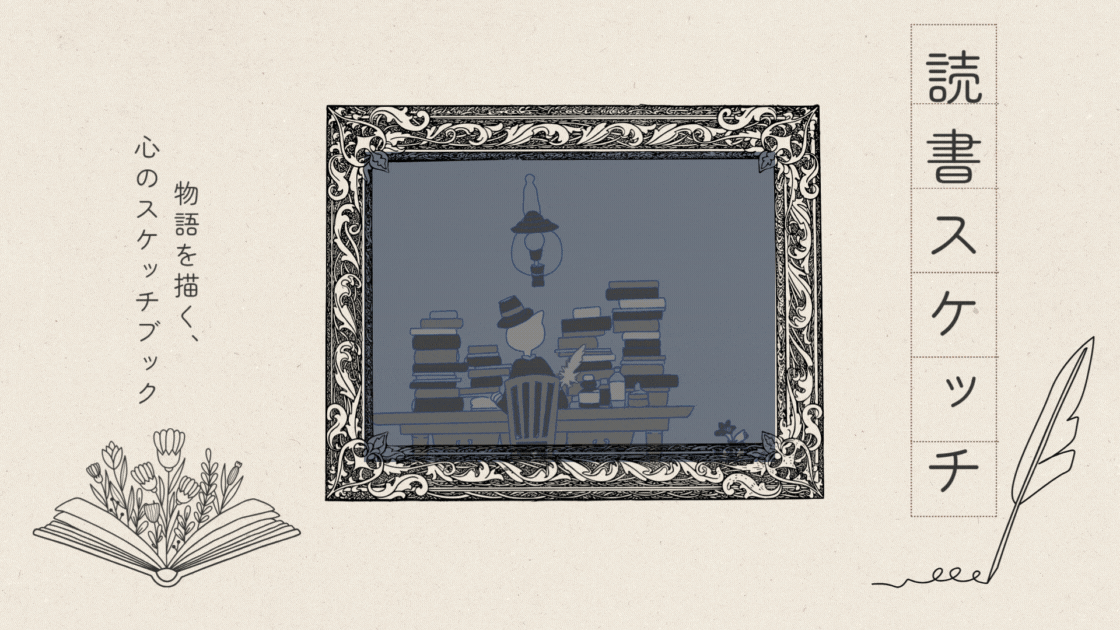


コメント